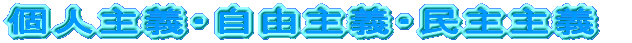
個人主義
A 個人主義の根源
現代社会の思想の核は、個人主義である。しかし、その個人主義が思想として確立されていない。現代社会の不毛さの原因がそこにある。
個人は、自己を客体化したものである。
自己の客体化という意味以外に、個人は、一個の人間という意味、個としての人という意味もある。前者は、生物学的な意味をもち、後者は、社会における最小単位という意味をもつ。つまり、 個人は、生物的、社会的属性を併せ持っているのである。
個人主義思想の根源は、自己にある。個人主義が思想として確立できないのは、自己の定義が曖昧だからである。
個人の定義をする為には、まず、自己の定義をした上で、それを再度個人の定義に変換するという二重の手続きが必要である。個人の定義が曖昧なのは、この手続きの複雑さにも一因がある。
自己とは、何か。まず、自己とは、すべての存在の前提だと言うことである。自己は、唯一な存在、絶対な存在である。次に、自己は、存在それ自体である。そして、自己は、独立し完結した存在だと言う事。つまり、自己は、それ自体で存在している。また、自己は、自己の唯一の体現体だと言う事。つまり、自己を、体現できるのは、自己だけなのである。そして、自己は、主体であるという事。認識主体だと言う事。また、自己は、今しか存在しない。そして、自己は、霊的な存在である。最後に、自己は、間接的、認識対象だと言う事である。
自己の存在を証明するのは働きである。言い換えると自己は働きだと言える。
自己の働きには、第一に、認識のはたき、第二に、意識の働き、知識の働き、第三に感情の働き、第四に、意志の働き、第五に、心の働き、第六に、欲望の働き、第七に、論理の働き、第八に、フィードバックの働き。第九に、肉体の働きがある。
第一の、認識の働きは、視覚、味覚、聴覚、嗅覚、触覚の五感によって為される。第二の、意識の働きは、認識によって得られた情報を分類し、再統合する過程で形成される。第三に感情の働きは、喜怒哀楽、好き、嫌い、恐怖、驚愕、苛立ち、和み、癒やし、愛着、親近感、信頼、甘え、無視、逃避、脅迫、命令といった情動によって為される。第四の、意志の働きは、決定や決断を促す働きである。第五の、心の働きは、情動によって形成される愛憎怨恨と言った働きである。第六の、欲望の働きは、生物として生きる為に必要な働きである。第七の論理の働きは、推定したり、分析したり、判断する為の順番や手順、基準を形成する働きである。第八のフィードバックの働きは、外部に対する働きかけに対する外部の反応を取り込んでいく働きである。第九の肉体の働きは、自己を外部に表出する為の働きである。
認識は、好奇心、興味から始まる。
自己の外側に広がっているのが物の世界である。自己の内側に形成されるのは、事の世界である。
認識は、意識を深める働きがあり、意識は、判断基準、行動規範や価値観、倫理観の基となる。
認識が意識に昇華する過程で論理的働きは定型化され、認識によって得られた情報は、知識へと発展する。
論理は、判断を標準化する働きがある。
自己以外の認識は、直接的な手段によって為される。
それに対して自己認識は、一旦、外に自分を投影し、自己を客体化する事によって為される。
相手の欠点や過ちに気がつくという事は、自分の内面にもそれに呼応する要素が隠されている。
つまり、同質の欠点や経験がある場合が多い。
人を責める前に自らを省みよ。
他人を通じて自分を知るのである。
感情は、自己の内面を外部に表出する行為である。
感情は、肉体を通して言葉、表情、仕草、動作、態度といった行為によって外に表現される。
中には、暴力と言った強い表現もある。
感情表現には、基本的に、笑う、泣く、怒鳴る、罵る、喚く、叫ぶ、苛立つ、目をそむける、逃げる、飛び上がる、暴れる、脅すといった行動によって外へ表出される。
無視や沈黙、無表情も感情表現の一種である。
感情表現は、一般、特定の対象に向かって表出される。
外に向かって感情が表現されると、行為として表現された感情を自己も認識して自己の内面を知る。
外に向かって表出された感情表現によって外部の対象も自己も自分の意志を確認し、確定する。
それをいったお終いよという事にもなる。
感情によって表現されるのは、基本的に攻撃と防御、又は、受容と拒否であり、具体的には、反抗、逃避、受容、承諾、合意、決意、無視、威圧、脅迫、焦り等がある。
感情は、決断を促す働きがある。
感情は、結果や現象のように表面に表れた事象に対する働きを言う。
原因に対する感情は結果に対する感情から生じる。
感情の中で喜びや怒りは能動的な働きをする。悲しみや楽しみは、受動的な働きをする。
また、喜びや楽しみは肯定的な働きをし、怒りや悲しみは、否定的な働きをする。
感情の能動的な働きは決断を促し、受動的な働きは、決断を抑制し、鈍らせる。
感情は、意識を高揚させる働きがあり、論理は、意識を鎮める働きがある。
意志の働きは、決断の方向性を定め、安定させる働きをする。
意志は、善に対する志向である。
善は自己善である。
勇気は、意志より発する。
心は、感情の多様性を制御する。
心は、感情を一定化し、定着させる。
嫌悪や苦痛、恐怖は、嫌悪感を抱かせたり苦痛を与える対象に対する憎しみとなる。
和みや癒やし、親近感、信頼感は、愛着となり愛情へと発展する。
愛情は、甘えによって表現される。
心は、空想や想像の根源である。
心は、記憶や思い出の収納庫である。
判断は、人の意見を聞いて、決断は自分の力でする。
判断は論理的にされ、決断は感情的にされる。
論理的働きを最も純化した体系が数学的体系である。
論理は知識を体系化する。
決断は、行為として外部に表現され、内と外に働きかける。
行為は、自己の外部と内部に対して同時に作用する。
自己の内面と外界に対する働きかけは、内面と外界に対して作用反作用の関係を生じさせる。
自己の行為による外界の変化と内部の変化は、経験となる。
経験は、外的事象として認識される。経験は、内部にフィードバックされ、意識に蓄積される。
内面と外界との働きかけは、例えば、引力と斥力の関係のように正と負の働きによって均衡させようとする。それは、引力と斥力の関係のようにてある。
反発や反抗は、自己の自立的行動の表れである。
自己は、肉体を通して、一旦、外へ投げ出される。
自己は、外へ表現されることによって認識対象となる。
自己の姿は、鏡に映されて認識対象となる。
自己は、鏡に映された自分の姿を見て、自分の肉体の形を知る。
感情も行為として外部に表現される。
表現されることで、自己の心の動きを明らかにすることができる。
心を作り上げるのは、自分の思いなのである。
思いが強すぎると心の働きが負担となる事がある。
心は、行動を制御する働きがあるからである。
思いはその時々に感情として表出される。
自分の思いは、自己の内面に発生する。
思いは無形である。
故に、思いは外部に向かって行為として表される事によって対象化される。
行動は、経験として心の奥底にしまい込まれる。
思いは感情として表現される。
人間は、自分の心の動きも外に映さないと理解できない。
特に、言葉が重要な働きをする。
言葉は、自分の行為に意味づけする。
文章は、さらに自分の思いを心に定着させる。
嘘でも、言葉に出したり、文章にすると真実のように思い込む危険性がある。
嘘も現実となる事がある。
歴史的記録は絶対ではない。
過去の記憶は、不確かなものである。
それを前提としなければ歴史の真実は理解できない。
多くの歴史は思い込みの産物なのである。
意味は、言葉によってもたらされる。
自分の愛情は、行為として相手に示され、行為として表れたメッセージに対する相手の反応によって意識に還元される。愛する事は、愛される事によって確認される。しかし、必ずしも自分のメッセージを相手が受容するとは限らない。そこに意識の複雑さがある。相手の反応によっては、 愛に対する意識は形成されるのである。
自他の関係が意識を形成する上で重要な働きをする。
この自己の働きと外界の働きの相互作用が人間の社会と一人の人間の人生を作り上げていくのである。
恐怖は、恐怖を抱かされる対象に対して忌避、回避する行動を触発させる。
恐怖は時として怒りに転化する。
怒りは、怒りによって増幅され、悲しみによって抑制される。
怒りは、怒りの対象に対して攻撃的にさせる。
相手に怒る要素がないのに、相手が怒っているように感じるのは、相手に自分に怒りが反映されている事が原因している場合がある。
相手に投影されている自分の怒りを相手の怒りとして受けとめるのである。
相手が平静を装っている時には、相手の癇(かん)に障るようなことを言ったり、不快な行為をする事によって相手の怒りを誘発し、自分の怒りを相手に転移させる事もある。
相手に自分に怒りを転移させる事によって怒りを共有化するのである。
感情を共有化する事で共通の価値観や合意を形成し、また、感情を増幅する。
そして、心の底に植え付けるのである。
怒りを核とした集団が形成される事もある。
同様に、悲しみを核とした集団、喜びを核とした集団、癒やしを核とした集団を形成する事も可能である。
しかし、最も、激しい行動を誘発するのは、怒りを核とした集団である。
怒りは、時として社会を変革する為の原動力となるのである。
人と人との関わり合いの中で人は成長し、社会は発展していくのである。
この関係は、人間が生まれた時から構造的に設定されている。
人は、生まれたばかりの時は、一人では生きていけないようにできている。他人の力に依存しなければ生きていけない。他者に依存し、関わる事で、認識が深められていく。依存している対象から意識の原型が継承されていく。又、自分に必要な者や事は、好ましく、危険な物や事は、不快に感じるようにできている。
赤ん坊は、母親の注意を自分に向ける事に最大限の労力を使う。
自分に注意を向けさせる為の感情表出が外界への働きかけの第一歩となる。
ここで定義された自己を客体化すると個人の定義になる。
自己の定義を個人の定義に置き換えると、自己が、全ての存在の前提であるということは、個人も、全ての対象の前提となる。自己が、唯一な存在、絶対的な存在であるという事は、個人は、人的要素の最小単位である事を意味する。自己が存在それ自体と言う事は、個人も、存在以外の属性を持たない、素の存在物だという事である。また、自己が独立し完結した存在と言う事は、個人は、個人として他から独立した単体である。自己が、それ自体で存在すると言う事は、 個人は、自立した存在だと言う事である。そして、自己が自己の唯一の体現体だという事は、個人意志や存在は、その個人しか外部に、表現できず、その権利も責任も、個人に帰属することを意味する。また、自己が主体的存在であるから、個人は、主体的な存在である。この様な自己が、今しか存在しないという事は、個人の立場や考え方、行動は、刻々変化していることを意味する。そして、自己が霊的な存在であるという事は、個人は、生き物であることである。最後に、自己が間接的認識対象であるという事は、個人は、外界との関わり合いによって自分を立場を理解し、位置づけることを意味する。故に、個人は、必然的に、社会的存在になるのである。
また、自己は、間接的な認識対象であることによって、個人が社会に及ぼす働きは、内的な世界と外的な世界に同時に発生し、その関係は、作用反作用の関係になる。
権利と義務、権限と責任は作用反作用の関係である。教育は、権利であると同時に義務であるというように、権利と義務は、作用反作用の関係にある。
そして、権利と義務は、国民一般が一様にもつ力であり、権限と責任は、任意の個人がその立場に付随して持つ固有の力である。
個人が一切の属性を持たない素の存在物であり、人的要素の最小単位だと言う事によって、個人の価値観のような属性は、全て相対的なものとなる。つまり、人間が判別した物は、全て相対的な物となる。何らかの価値基準が介在した物は、全て相対的なのであり、絶対的なのは、何の基準も存在していない素の対象、即ち、自己と神だけなのである。そして、自己が転化して個人を最小単位とすることによって、相対的な価値観から受ける社会の歪みを最小限に抑止しようというのが、民主主義の原理なのである。
個人は、主体的存在である。個人は、認識主体である。個人の幸せは、その人しかわからない。それが個人主義の前提である。そして、個人主義者にとって、結局、人生の目的は、自己の幸せを追求することだ。そこで問題なのは、幸せの中身である。そして、個人主義では、個人の幸せは、純粋に個人に帰属すると考える。だから、何を幸せとするかは、個人の自由である。ただ、個人主義社会では、他人の権利を侵さないかぎり、個人が自己の幸せを追求する事を妨げてはならない。それは、個人が個人の幸せを追求する事を個人主義者は、当然の権利と見なすからである。
自分の見る世界しかわからない。他人の痛みは、基本的にはわからない。推測する以外にないのである。同様に、個人の幸せは、当人しかわからないという事が前提である。故に、個人主義社会では、自分が、どのような幸せを望んでいるかを申告することが前提である。なぜなら、それは、第三者が伺い知ることが、できないからである。個人主義国では、申告することによって権利が発生する。申告しなければ権利は無効となるのである
同時に、自分の事は、自分が責任を全て持たなければならない。個人の行為は、個人の責任に帰属するからである。また、個人の権利を成立させる根拠もそこにある。
Since 2001.1.6
本ページの著作権は全て制作者の小谷野敬一郎に属しますので、一切の無断転載を禁じます。
The Copyright of these webpages including all the tables, figures and pictures
belongs the author, Keiichirou Koyano.Don't reproduce any copyright withiout
permission of the author.Thanks.
Copyright(C) 2001 Keiichirou Koyano