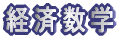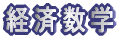一とゼロと無限
一とゼロと無限。始まりは一である。一から始まると距離ができる。距離がゼロを生む。無限は、ゼロと一との間にもある。
無限に収束し、又、無限に発散する。
無限を極めると全体と部分に至る。その時、無限は、全一かゼロに向かう。
一は無限へと連なる。一が無限に発展する。そして又、一と0との間に無限が生じる。
無限は、時間が陽に作用する場合は、永遠となり、陰に作用する場合は、普遍となる。
数の集合、数直線は、一つの次元を構成する。数は、無次元の量である。
次元は、距離と順序をもたらす。
二数の積は、長方形の面積として表すことができる。三数の積は、立方体として表すことができる。長方形の面積は、数と数の積である。数は、距離を表す。距離とは、長さ、熱さ、厚さ、重さ、高さ、価格、時間などを言う。長さだけが距離を意味するのではない。
貨幣単位は、自然数の集合である。貨幣価値は、数列で表される。自然数は、無限集合である。貨幣は、無次元の量である。
財政規模の限界線は、貨幣の発行総量によって決まる。貨幣は、自然の数の集合である。財政は、貨幣の集合である。財政は、発散するか、収束するかは、財政構造、数の有り様によって決まる。
事象を無限に突き詰めると極限状態になる。極限はゼロに至る。ゼロは、無ではない。ゼロを極めると存在に至る。存在は、瞬間にある。時間は、瞬間の延長線上で連続する。
無限に細分化された切片を繋ぎ合わせると実体が現れ、今という瞬間を結び付けると時空間が現れる。実体と時空との接点は、傾きである。
無限は、宇宙である。何もこの無限の宇宙は天空にのみ存在するのではなく。極小の世界にも存在する。そして、この無限は零の世界にも通じているのである。
我々は、現実の生活に置いて無限の対象を問題とすることは稀である。あってとしても範囲を特定して無限を対象とすることを回避する。それが現実的対応である。ところが数学では。無限こそが主題となる。
存在には限りがない、かぎりあるのは自己の側である。時間には限りがない。しかし、人間の一生には限りがある。だから、人間は、限界を設けてその境界線の範囲内で生きていかざるを得ないのである。
大地を切り刻んで土地を所有権を主張するのは人間である。一定の範囲の土地に所有権が生じると土地は、財となり、価値が生じる。
空を飛ぶ鳥には、縄張りはあっても土地の所有権の意識はない。だから、空を飛ぶ鳥に人間が所有権を主張しても意味がないのである。
鏡を向かい合わせにすると無限の世界が拡がる。無限の世界は、遠いところにあるわけではない。自分の身近にも、日常的な空間にも潜んでいる。
この瞬間に永遠があり、極限に無限があり、極小の世界にも宇宙がある。
数は無限である。それが細部に向かえば極限になる。
拡げてみれば無限になり、突き詰めてみると極限に至る。
無限に拡散するのか、一点に収束するのか。
数から意味を取り去る働きがあるのがゼロと一である。数に意味を持たせるのもゼロか一である。極限も無限も一とゼロの狭間にある。
ゼロは、存在であり、無限である。一は、自己であり、自己は一である。自己は。、対象に投影されて単位となり、対象は、単位を切り取られて一となる。単位は、自己に反映されて二を生む。二は、自己に還元されて三となる。神は、ゼロであり、無限である。意識は、ゼロと一と無限の間に生じる。
ゼロと一との間に何があるのか。ゼロの概念が確立されるまでは、始まりは一であった。ゼロと一との間の空間は存在しなかった。
ゼロ才というのは、年齢はなかった。それが数えである。しかし、ゼロが発見されてからは、ゼロから一のでの時間が生じた。ゼロは無ではない。空である。
ゼロは、始まりである。ゼロ以外の数は、ある意味で通過点に過ぎない。ゼロがあってはじめて幅が生じ量が認識されるのである。
∞(無 限)
一、十、百、千、万、億、兆、京、垓、𥝱(秭)、穣、溝、澗、正、載、極、恒河沙、阿僧祇、那由他、不可思議、無量大数(計21単位)
小数 分、厘、毛、糸、忽、微、繊、沙、塵、埃、渺、漠、模糊、逡巡、須臾、瞬息、弾指、刹那、六徳、虚空、清浄、阿頼耶、阿摩羅、涅槃寂静(計24単位)
数の単位は、神秘的で、宗教的である。
恒河沙(ごうがしゃ)阿僧祇(あそうぎ)那由他(なゆた)不可思議(ふかしぎ)無量大数(むりょうたいすう)
「恒河」はガンジス川を意味する梵語 "Ganga"を音訳したものである。すなわち、「恒河沙」とはガンジス川にある無数の砂の意味であり、もともと無限の数量の例えとして仏典で用いられていた。
阿僧祇は元は仏教用語で、梵語を音訳した「数えることができない」の意味である。意訳では「無数」となる。仏典では、成仏するまでに必要な時間の長さである「三阿僧祇劫」という形で用いられることが多い。
那由他は元は仏教用語で、梵語の"nayuta"を音訳した、「極めて大きな数量」(新村出編 『広辞苑』第三版)の意味である。
不可思議(ふかしぎ)は語源は名のとおり、思ったり、議論したりすることが不可なほど大きい数字、ということから名づけられた。
無量数は仏教用語からとられたものである。
漠とは、果てしなく広々としている様という意味ととりとめがなくハッキリしていない様と言う意味がある。
模糊とは、ぼんやりとしたという意味がある。
逡巡とは、ためらいである。
弾指とは、爪弾き、転じて、極めて短い時間を意味する。
刹那とは、時間の最小単位、爪弾きの六十五分の一という意味がある。どちらも仏教用語である。
何れしても極小の世界は時空間的な捉え方がされている。
虚空は、空虚ともかく。空間や平面に何もない様を言う。
無限は、諸行無常,変化(へんげ)に通じるのである。
阿頼耶(あらや)とは、唯識思想により立てられた心の深層部分の名称であり、大乗仏教を支える根本思想である。眼識・耳識・鼻識・舌識・身識・意識・末那識・阿頼耶識の8つの識のうち第8番目で、人間存在の根本にある識であると考えられている。ālaya
の語義は、住居・場所の意であって、その場に一切諸法を生ずる種子を内蔵していることから「蔵識」とも訳される。(出典 Wikipedia)
阿摩羅(あまら)とは、阿頼耶識からくる。唯識思想(法相宗)では、八識を説く。 すべては阿頼耶識より縁起するとし、主に迷いの世界であるが悟りも阿頼耶識より生じるとする。
一方、心は本来清浄であるとする如来蔵思想があった。(出典 Wikipedia)
そして、涅槃は、究極的な空間や境地を意味する。ここまでいくと極小の世界は、時間も空間も超えた次元へと昇華されている。
ここには、無限の持つ意味や世界が凝縮されている。
極大にしても、極小にしても、様を意味する。様というのは、物事の有り様、様子である。又、姿形を言う。つまり、極大、極小の数字は、古代インドでは、様相を意味すると考えられていたのである。
無限の前に無数がある。無数が変じて無限となったのである。
数は限りがない。無限とは数限りないことを意味する。
数が、0を認識し、自然数を形成した時点で、数は限りがなくなった。限りがなくなれば無限が成立する。則ち、数の天井がなくなる。上に開放されるのである。それが無限の一つの意味である。
無限には、もう一つの意味がある。
それは、細かく刻んでいくことによって生じる無限である。極小の世界にも無限がある。そして、その極致が涅槃なのである。涅槃とは、死後の世界であり、境地である。極小は、突き詰めると境地となり、世界になる。
0にも無限にもインドの思想、哲学が色濃く影響を及ぼしている。
限りない世界には、開かれた意味もあり、また、閉ざされた意味もある。それは、無限が、発散的でもあり、又、収束的でもある事を示唆している。
この発散と収束と言う動きが微分、積分の根底を形成することになる。
経済データで重要なのは、データの性格が発散的か、収束的かである。貨幣価値は基本的に発散的な性格を持っていることに留意しておく必要がある。なぜならば、貨幣価値は自然数だからである。自然数である貨幣価値は、放置すれば発散する性格を持っている。
自然数は、割り切れない分数を含まないからである。
純粋数学では、有限な事象をいかに無限の問題に置き換えるかが重要になるが、経済数学では無限な数列をいかに有限な数列にするかが重要となる。その為には、範囲の特定が鍵となる。
数字以外の意味、属性を取り去る。数字は本来無意味である。無意味だから働く。しかし、現実に当て嵌めようとすれば、数字に意味を持たせる必要がでてくる。
人間は、最初から対象を無限な存在として捉えたりはしない。最初は、何でも限りある存在として認識する。ただ、対象を認識している内に割り切れない存在にぶつかるのである。そう、割り切れないという事である。割り切れない対象に無限は潜んでいる。そして、無限はあらゆる対象に潜んでいることが段々に分かってくる。
純粋数学が抽象化の過程ならば、経済数学は、具象化の過程である。
無限は内的な世界に宿す。無限は人間の意識の内にある。無限は、自己の内にある限界が生み出すのである。それは、内と外とを結ぶ物体、肉体の限界によって生じるのである。
貨幣価値を無限に拡散するのは、人間の意識である。なぜならば、価値は人間の意識が創り出すものだからである。だから、貨幣価値を抑制できるのは人間の意識だけなのである。
人間の住む世界は、有限な世界である。人間の一生にも限りがある。人間が所有できるものにも限りがある。この世の全てのものを食べ尽くすことなどできないのである。
しかし、貨幣価値には、際限がない。人間の欲望にも際限がない。際限の貨幣価値と人間との欲望が結びつくと限度を失う。有限なる存在が無限を志向した時から過ちが始まる。人間は全知全能な存在にはなれない。故に、怖れよ。
人間は、自らの限界を自覚した時、真っ当になれる。自らの限界を知らぬ者は愚かである。そして、人間は、限界を忘れた時、身を滅ぼすのである。
つまり、貨幣的空間では、開かれた空間、開かれた集合をいかに閉ざすかが問題となるである。
貨幣が作り出す空間は
数学的空間である。
貨幣的現象は、物理的現象より余程数学的である。
時間が加わることによって無限の空間が生じる。資本主義は、会計制度の上に成り立つ思想である。会計制度は、継続的事業を前提としている。当座的事業には、始点と終点を前提して成り立っていた。継続的事業は、始点は前提とされるが終点は、無限の未来である。故に、継続的事業を前提とした時から経済は、無限の概念が入り込んだのである。現代経済は、無限の支配下にある。継続を前提として単位期間の実績が計算される。利益は、局限なのである。それが期間損益の前提となる。
だから、現代の経済の実相は、積分的であり、また、変化は、微分的なのである。
全体を最大と見るか。最小と見るか。
全体を無限と見るのか、部分が無限と見るのか。
全体は部分に宿る。
経済において物質的空間を無限な空間として認識するか、有限な空間として認識するか、それによって経済に対する見方にも差が生じる。無限とは開かれた空間であることを、有限とは閉ざされた空間であることを意味する。
水や空気は無限にあるのか。資源は無限、無尽蔵に生じるのか。それとも限りがあるのか。人間に与えられた時間は無限にあるのか。それとも限られたものなのか。
限界を意識するか、しないかによって、人間の有り様、社会の在り方も違ってくる。
経済は、数列として表される。貨幣体系は、自然数の数列であり、上限がない。貨幣価値で表される数列は、無限数列であり、制限がない。数列間に働く相互牽制によって、数列は、限界が生じ抑制される。数列は、抑制がなくなると無限に発散する。重要なのは、数列間に働く作用である。
貨幣価値は自然数の集合である。自然数の集合は、0から無限へと繋がる。
故に、貨幣価値は、常に、無限の脅威に曝されている。
貨幣経済の現象や事業は数列として表現することができる。それは貨幣経済も事業も貨幣制度を基礎として成り立っており、貨幣は数だからである。故に、貨幣価値は数直線として表現する事が可能であり、価格も、数直線として表現する事ができる。
貨幣価値は、極言すると数である。貨幣価値は、自然数の集合であり、数直線と見なす事ができる。この様な貨幣価値は、開かれた状態では、無限に拡散する。故に、境界線を画定し、範囲を特定することによって空間を閉ざす必要がある。
なぜならば、貨幣価値は、比だからである。
貨幣制度や通貨政策というのは、無限に拡散していこうとする貨幣価値をいかに抑え込むかという事が、最大の問題なのである。
貨幣は、当初、補助的な手段に過ぎなかった。
貨幣は交易のための手段、道具である。それもはじめは、補助的な手段、儀礼的な手段に過ぎなかったのである。
物々交換も最初は自給自足できない物を市場で交換する。もしくは、生産的労働に従事しない者、即ち、政治的権力者や宗教的行事に携わる者に対する貢ぎ物の必要から生じた行為である。つまり、本来は、自給自足が原則であって自給自足できない部分を補助する手段として、物々交換が始まり、やがて貨幣へと発展したのである。
この様な貨幣は、当初、経済活動を主とした物と言うよりも儀礼的な物から始まった場合もある。しかし、市場が形成されるのに伴って物と物との交換を仲介するが貨幣の役割となり、今日のような貨幣経済が形成された。
貨幣は、貝殻の様な物品貨幣、砂金や金、銀の塊、実物貨幣から、金貨、銀貨、銅貨といった鋳造貨幣へ、そして、金本位制による兌換紙幣、さらに、不兌換紙幣へと移っていたのである。
特に注意すべきなのは、鋳造紙幣から表象紙幣への移行、そして、兌換紙幣から不兌換紙幣への移行である。それは、物から表象への変化であり、物による制御から仕組みによる制御への変換を意味することである。
兌換紙幣から不兌換紙幣への変化は、物から仕組みによって制御する時代に変化したことを意味する。
貨幣単位は、無次元の量である。
貨幣単位は、無次元の量である。
貨幣価値は、貨幣単位と物的量、又は、時間的量の積として表される。故に、貨幣価値は、線形的だと言える。即ち、貨幣経済は、線形代数として表現できる。
貨幣単位は内包的量であり、物的、時間的量は、外延的量である。貨幣価値は、内包的量と外延的量の積として表現される。
市場に流通する貨幣の総量を画定するのは、貨幣の運動と貨幣の発行量、貨幣制度の仕組みである。貨幣価値は、取引を通じて市場に現れる。貨幣の運動は、取引を仲介する形で実現する。取引は、物の流れと分配を意味する。物の流れは、物の交換によって発生する。即ち、需要と供給関係によって形成される。
貨幣価値の上限を画定する働きには、貨幣と財の関係が重要な鍵を握っている。その下記を解き明かすためには、物の流れと貨幣の流れの関係、そして、その流れによって生じる働きを知る事である。
貨幣の流れる方向と逆の方向に財は流れる。この貨幣の流れと物の流れが逆方向の働きを生み、貨幣価値を制御する働き、即ち、無限に拡散するのを防ぐ働きをするのである。
つまり、単位貨幣の価値は、国内に流通する貨幣の量と財との一対一の関係と外部から流入する物資と単位貨幣の価値との関係によって決まる。
財政政策を決める場合、必要なのは資金の流量を割り出すことである。それは、換言すれば、流通する資金の必要量をいかに算出するかと言う問題である。
なぜ、必要な資金を割り出すのかというと、財政には、貨幣価値の上限を画定する働きがあるからである。
貨幣は、循環する事によって効力を発揮する。貨幣を循環させるためには、国家が、貨幣の放出と回収を繰り返す必要がある。
貨幣の回収は、強制的に徴収するか、借りるかによってなされるしかない。強制的に徴収するのが、税であり、借りる為に発行されるのが公的債券、即ち、国債である。
レパレッジというのは、金利相当部分を基礎として掛けられる。
ある意味で、流動性を確保できさえすればいいのである。つまり、固定的部分を仮想してレパレッジを掛けることも可能である。それが信用取引である。
貨幣価値は貨幣が流れている部分によって形成される。貨幣は、流れている部分によって効力を発揮する。
レパレッジが利きすぎると貨幣単位の濃度が薄まってしまう。
貨幣価値は、市場の信認を裏付ける物や仕組みを失えば際限なく低下する。貨幣価値は、数値的価値であり、自然数の集合である。何等かの裏付けによって貨幣単位は保証されてきた。実物貨幣の時は、貨幣その物が価値を持っていた。兌換紙幣までは、例え、名目的と言っても金という実物によって貨幣単位は、保証されてきたのである。不兌換紙幣は、金の保有量という制約から開放された反面、物としての裏付けを失った。何も裏付けがなければ、貨幣は、開かれた空間となり、一度、貨幣価値が下落すると歯止めがなくなる危険性がある。それが、ハイパーインフレである。
ハイパーインフレになると貨幣価値が抑制力を欠いてしまう。その様な状況下では、タバの様な実物が貨幣の変わりをする例さえある。
需要を満たすだけの財が十分に供給されている場合は、貨幣の流通量によっ価格は決定される。
経済の働きは労働と分配に集約される。
経済本来の役割は、労働と分配である。労働と分配を結び付けているのが貨幣の流れ。故に、貨幣の流れる量と速度が重要となる。
経済価値を決定しているのは、物と人である。人とは、所得、人件費を意味し。要するに付加価値である。そして、需要なのは、付加価値の多くの部分は為替の変動の影響を受けないという事である。つまり、為替変動に対して付加価値を構成する部分は、中立的だといえる。
国民総生産と国民総付加価値とは同義である。国民総生産は、国民経済の規模を示す指標の一つであることが、付加価値の意味を象徴している。
付加価値が為替に対して中立的であるために、付加価値の働きや動きが景気にたいし、又、国際的競争力に対して決定的な影響を及ぼすのである。
付加価値が為替の変動に対して中立的という事は、為替の変動に対して付加価値は、弾力性が乏しいことを意味する。その為に利益に対する圧迫要因になる。なぜならば、収益は、為替の変動に連動し、費用は、付加価値に連動しているからである。
付加価値の差が、国家間の競争力の差になる。そして、付加価値の差を左右するのは、為替相場、即ち、通貨の価値である。付加価値と貨幣価値との相関関係によって国際競争力に違いが生じる。
重要なのは、との段階、どの部分の価格に影響がでるのかである。つまり、原価段階なのか小売り段階なのかによって政策を変える必要がある。
競争力と言ってもどの段階での競争力を言うのかを考える必要がある。例えば、原材料段階なのか、原価段階なのか、卸売り段階なのか、小売り段階なのか、それによって付加価値の所在に差がでる。公正な競争と言っても最初から価格的に太刀打ちできないような条件で競争を強いられたら、産業は成り立たなくなる。かといってやたらと関税を引き上げ、市場に壁を作れば交易そのものが成り立たない。公正な競争は、前提条件から判断されるべきなのである。
物で重要な要素、輸入量、生産量、消費量、在庫量、輸出量である。
物の経済とは、物資の調達も生産、分配、消費などを言う。基本は物流である。そして、物流を起こすのは取引であり、取引は交換を意味し、取引を仲介するのが貨幣である。貨幣の流れの反対方向に物は流れる。この流れが物資を分配するのである。重要なのは、生活に必要な量だけの物資が常に市場に供給されているかである。
元々、産業革命以前の時代では、慢性的な物不足の状態が続いていたのである。
生産力の増大に伴い、生産コストの劇的な低減がはかられ、その一方で所得の恒常的上昇が続いた。これは、人類史上でも希有な現象なのである。それを常態だと錯覚した。それが現在の経済の状況を解りにくくしているのである。
問題は、必要な物資が、必要な量だけ市場に供給されなくなったときである。また、例え、必要なだけの物資が市場に供給されたとしてもそれを購入する手段を最終消費者が持っていない場合なのである。それが経済の根本的な問題なのである。
市場経済が成り立つ為の要因は、必要な物が必要なだけ市場に供給され続けているという事と、それを購入するための手段を最終的な消費者が万遍なく所有しているという事であり。それを実現するためには、どの様な仕組みが必要なのか、それが、経済の本質的な問題なのである。
貨幣価値は、人の欲求に基づく需要と物の生産力に基づく供給、そして、貨幣の流通量によって求められる。
貨幣の適正な流通量は、どれだけの量の貨幣が必要なのか、なぜ、必要なのかによって求められる。
そして、貨幣の必要量は、市場の取引量に比例する。
また、為替において単位表裏の関係にある。つまり、一方が上がれば一方が下がるのである。
貨幣価値を維持するためには、貨幣価値を保証するものか仕組みが必要となるのである。
金貨、銀貨では、貨幣重要に必要な量だけの金や銀を調達しなければならなかった。金本位制度では、貨幣の需要に見合うだけの金を準備する必要がある。当然、貨幣の量には限界が生じた。
不兌換紙幣による貨幣制度に変換される以前には、物によって貨幣価値を保証する制度だったのである。不兌換紙幣への移行は、この様な物による直接的な保証から単位貨幣間の相互牽制に基づく仕組みによって保証する制度に変わった。つまり、物から仕組みへと変化してきたのである。
物価が、貨幣の総量の重しになっている。
国内の物価を決定する要素は、金利、財政、所得である。
そして、現在の貨幣価値の単位は、国際的な貨幣制度によって維持されている。
この事は、一つの貨幣単位の崩壊は、すぐに、通貨制度全般に波及する危険性があることを意味している。
不換紙幣、変動為替制度というのは、複数の単位貨幣が商品取引を仲介にして価値の均衡を保つ制度である。
円とドルとの関係を例にすると、円の上昇は、即ち、ドルの下降を意味し、円の下降は、ドルの上昇を意味する。ドルの上昇は、円にとってはドル建ての財の価格の下落を意味する。これは輸入品の価格の下落として市場に反映する。逆に輸出品の上昇を意味する。国内の物価には、輸出品の価格は反映されないから、輸入額だけの物価の減少を招く。反対に輸出品の上昇は、輸出量を抑制する働きがある。輸出品の抑制は、円の下降圧力して作用する。
この様に、経常収支を一定に保とうという圧力が国際市場において単位貨幣には働く。
また、経常収支と資本収支は、国際取引では、均衡させておく必要がある。
貨幣価値を制御するための国際的な仕組みは、複数の貨幣単位と、国際間取引、決済のための準備資金、準備資金の為の貨幣を発行する仕組み、国家間の経常収支と資本収支、為替市場などからなる。
市場の需要の量を問題とする場合、基本となるのは、個々の経済主体の購買力の問題であり、購買力は価格と資金量の関数である。
内部にどれくらい外部から物資を購入するための資金量があるかという問題である。つまり、資金の蓄えと調達能力が問題となる。それは、国家においても、企業においても、個人においても同じである。どれだけの購買力があり、どれだけの蓄えがあるかである。
そして、その上で決済のための資金をどれだけ公的機関が用意できるかなのである。
現在、決済に必要な資金は、基軸通貨国であるアメリカが、国債を発行し、基軸通貨国以外の国の中央銀行、政府、金融機関、投資が購入することによって作られている。
今後は、国際的国債の買い取り機関を設立し、国債を担保として決済通貨を発行する制度の検討も必要だと考えられる。
最終的には人件費の問題に還元される。
最終的に核となるのは、人件費、即ち、個人所得の水準である。なぜならば、第一に、人件費というのは、為替の影響を受けず、費用の核となる部分を形成すると言う事である。核となる費用は、付加価値を意味する。第二に、人件費は裏返せば所得であり、支出、即ち、消費の原資を構成する部分だからである。国民総生産(付加価値)と国民総所得は表裏をなす概念である。両者は、原則的に等しい。
つまり、物価を形成する基礎的部分が人件費だと言う事と、貨幣価値で硬質な部分が人件費によって形成されるという事である。それは、国内の産業の競争力の基準となる。人件費が相対的に低いところは国際的競争力が強い。
その結果、全体は、一定の所得水準に均衡する方向に向かう。ただし、その際に問題になるのは、所得のバラツキや偏りである。
為替の問題は、貨幣単位の濃度と範囲の問題でもある。
貨幣単位は、財を媒体として結びついていて常に相互に反対方向の力が働いている。つまり、単位貨幣の価値が上がれば物の対外的価値は減少する。
つまり、通貨圏の内と外の働きと通貨圏内部の貨幣の働きが単位貨幣を範囲を画定しているのである。
故に、通貨圏の外部の物と貨幣との関係と動きと通貨圏内部での物と貨幣との関係と動きを別個に考えた上で関連つける必要がある。
通貨圏の外部の物と貨幣との関係、動きと内部の関係と動きを区分するためには、通貨圏内部から見て物と貨幣がどの様な動きをするかを先ず明らかにすることである。
その為には、為替に連動する財と連動しない財とを明確に区分することである。
基本的には、為替の変動の影響を受けないものは、国内にある物資だけで生産され消費される財と人件費である。
人件費は下方硬直的である。それ以外の物は価格の変動の影響を受けると言っていい。重要なのは、直接、為替変動の影響を受けない部分という事は、為替変動に対して硬直的な部分と言っていい。
為替、即ち単位貨幣の価値に比例して変化する費用は、一定の時間が経てば解消される費用である。しかし、為替の変動に連動していない費用は、通貨圏の外から見ると逆に為替の変動に伴って上下し、しかも長期に渡って制約される費用なのである。その典型が人件費なのである。その為に、産業の競争力は最終的には人件費に収斂する。
利益は、結果を意味するのではなく。基準や指標、尺度、目標を意味するのである。
利益は、費用を梃子にして作り出される。故に、費用の核となる部分、即ち、人件費が重要な役割を果たす。
人件費の働きには、第一に、労働に対する対価、収入、報酬、労働に対する評価としての働き。第二、人件費、則ち、生産や収益に対する費用としての働き。第三に、所得、則ち、生活費の原資としての働きである。
この様な働きの違いは、働きの影響を及ぼす対象の差として表れる。収入は所得格差や生活水準の差として現れ、人件費は生産や価格に影響し、所得は消費や物価を構成する。
人件費の働きが収入としての働き、費用としての働き、生活費としての働きそれぞれの方面に作用を及ぼし、経済を動かす原動力となる。
所得と人的資源の配分の関係は、社会的要請に基づいて形成される。所得格差は、社会構成の基礎を形成する。
プロスポーツの選手や医者が高額所得を得る事で優秀な人材を集めることが出来る。それは、則ち、所得格差を生じさせる。
突き詰めてみると、経済的価値を決めている要素は、物と人だといえる。
お金、お金と言うが、お金、即ち、貨幣は影に過ぎない。現代人は、その影である貨幣に捕らわれて身動きできなくなってしまったのである。それは、貨幣が悪いわけではなく。貨幣に捕らわれている人間の性(さが)である。人間は、貨幣という影に怯えて自らを破滅へと導いているのである。
経済というのは、生きる為の活動である。つまり、生活である。
人々の生活の根底を成すのは、労働と分配である。つまり、経済の仕組みの根本は、労働と分配の仕組みである。言い替えるといかに働きに応じた分配をする仕組みを構築するかが、経済の根本的課題なのである。
故に、経済問題の根底には、労働や所得の時間的、空間的な平準化、平均化の問題がある。
第一の問題は、人々の欲求を満たすだけの生産財があるか。これは質と量ともにである。 第二の問題は、生産財が人々に公平に行き渡っているか。少なくとも、生きていく為に 最低限必要な資源が行き渡っているかである。
人々の欲求を満たすだけの生産財があったとしてもその分配が極端に偏っていて、中には、生活も出来ないような国民がいる場合と、生産財そのものが不足している場合とでは問題な本質が違ってくる。
則ち、生活するために必要な財が確保されているか。財を流通させるために適切な通貨量があるか。通貨を分配させるための労働の仕組みが構築されているかが、経済体制の基本なのである。
財と通貨と労働の調和こそが経済を安定させるのである。
それを前提とした資産、負債、資本の構成が適正であるかどうかが、資本主義経済を持続させる要素なのである。
物事には、どんな時代にも、変化している部分と変わらない部分、変わっていい部分と変わってはならない部分があり、それらの根本は突き詰めてみると単純明快な基準に基づいているのである。
今の経済は、成長や技術革新と言った変化による力にのみ重きを置いている。この様な経済体制は、成長や技術革新と言った変化がなくなれば失速して経済の均衡を失ってしまう。産業には、急速に技術革新が進んでいる分野と古くからの技術を継承することで成り立っている産業がある。
成長や拡大、技術革新のみを経済の原動力としていたら、市場が成熟し、あるいは、飽和状態に陥り、変化の少ない産業は衰退していってしまうことになる。
変化の激しい産業は、人材の入れ替わりも激しい。技術も熟練を必要としていない場合が多い。
逆に、成熟し、古くからある技術に支えられた産業は、多くの熟練した職人を養っている。この様な産業は、経験が重要であり、高齢になっても仕事を続けることが出来る。そして、熟練を要する技術は、時間をかけて人から人へと継承されていくべき技なのである。
この様な職人の存在は、社会の安定にとっても不可欠な存在なのである。
そして、長い間変わらない産業も必要なのである。
経済の話をする時、殊更に数値を上げて説明する者がいるが、必ずしも、数値が経済の実体を現しているとは限らない。数値は重要であるが、問題はその背後にある実体であり、実体の本質を知るためには、数値の根拠や前提が重要となるのである。
職場における女性に対する差別はなくすべきである。しかし、同時に女性の仕事に対する偏見もなくすべきなのである。貨幣経済のみが経済の全てではない。貨幣価値に換算されない労働もあるのである。
経済を短期的に突き詰めてみると経済主体の収入に占める支出の項目の比率が基礎となる。
実際の経営の現場においては、資金の流れが生み出した債権、債務の大きさが問題なのではない。流れた量が問題なのである。そして、資金を不足しないように循環させることが目的なのであり、それを監視するために会計制度は機能しているのである。
その場合、資金をどの様に調達したのか。借入金によって調達したのか、投資なのか、収益なのかそれが問題なのである。
収益や費用は、期中に決済された勘定である。取引では、決済が重要な意味を持つ。
未決済な資金が流通する。未決済な資金は、債権と債務を生み出す。債権と債務は、資金の流れる方向に影響を与える。
経済においては、一人当たりというのが基本単位となる。その場合の指標として用いられるのが平均値である。その核となるのが所得である。則ち、一人当たりの所得の平均と分散が基本となるのである。
所得水準が一致点が物価の安定水準である。
経済量は時間の関数である。
経済量は時間の関数でもある。
資本主義経済下における経済現象や会計現象は、数列として表現できる。そして、経済現象や会計現象は、時間軸が加わると無限級数となる。
会計現象は、継続事業を前提として成立しているからである。そして、資本主義は会計的思想だからである。いずれも時間の関数である。
数列として表現された場合、重要となるのが差なのか、比なのか。即ち、等差数列としてみるか、等比数列としてみるかである。
事業で重要なのは、変化が率に影響するのか、幅に影響するのかである。率か幅か、それは差か、比かの問題でもある。
費用対効果を考える時、率か、幅かが重要な意味を持ってくる。それは比か差かの問題でもある。
会計現象は幾何学的に表現することが可能である。典型的なのは、損益分岐点図や損益や貸借の構成図、原価差異分析である。経済や経営の状況を図形化する事は、経済や経営を解析するための第一歩である。
固定費と変動費を見る場合、注目すべき点は、変動費と固定費の動きが、全体で見た場合と製品単位あたりで見た場合では逆転すると言う事である。つまり、内部構造の動きが全体と部分では逆転するのである。
それが収益構造に重大な影響を与え、営業活動に決定的な作用を及ぼしている。それは、経済の方向を大量生産、大量販売、大量消費型に向かわせるか、多品種少量、質を重視した経済へ向かわせるかの分岐点だからである。
つまり、量と変化の相関関係をどう解釈するかが重要になるのである。
経済的な価値とは、数量×価格×時間の関数である。
力は、対象に速度変化をもたらすものである。速度とは、距離を時間で割った値である。仕事量は、力に時間を掛けた値である。仕事は力積である。
距離とは、隔たりを意味する。距離を意味する隔たりは、基本的には物理的隔たりを意味するが、なにも物理的隔たりだけでなく、時間的隔たりや金銭的隔たりとしても問題はない。隔たりとは、幅である。つまり、隔たりは連続量である。
貨幣が発揮する力は、貨幣が流れる速度によって決まる。貨幣の速度は、貨幣価値の距離と時間の関数である。
経済量と市場に流通する貨幣価値の総量とは同値同量ではない。貨幣価値の総量と市場を流通する貨幣の量も同値同量ではない。
それは、決算書に表される総量と所有現金が違うようにである。
貨幣単位というのは自然数であり、数直線上にある。自然数は無限に存在するから境界線を確定し、範囲を特定しないと無限に発散してしまう。
貨幣価値の量は、債権債務の残高に基づく量と市場に流通している貨幣の量の総和である。
流動性というのは、市場に流れている貨幣の量を言う。
故に、貨幣価値の総和は、貨幣の発行量と流通する貨幣の回転数によって決まる。
資金の流れは、取引によって生じる。取引が行われていない部分には現金は流れない。
不動産のように、潜在的価値に課税することは、いわば、水の流れていない河から取水するような行為である。当然、水は違う河や湖から引くか、地下水を汲み上げて調達しなければならなくなる。
土地そのものに課税することと、地代に課税することとは、本質が違うのである。
成長段階の市場は、成長によって取引量が増加し、それに伴って貨幣価値の総量も増大する。それに伴って所得も増加する。故に、納税額も拡大する。しかし、市場が成熟期になる取引量は安定し、貨幣価値の総量も減少する。それに伴って所得の増加も頭打ちになる。故に、納税額も横這いになるか、減少する。
利益が重大な意味を持つのは、資金の流れとの相関関係を明らかにする上でのことである。利益が資金と結びつかなければ、損益を測定する意義は、かなり薄れてしまう。つまり、利益は、収益と費用の長期的均衡の状態を資金収支は、当座の経営の問題として結び付けられなければならないのである。
所得の源泉には、過去から引き継いだ部分と新たに生み出された部分がある。過去から引き継いだ部分の基礎となるのは量であり、新たに生み出された部分は、変化である。
微分・積分と経済
微分積分は、経済に役立つのであろうか。経済で重要なのは、変化の実相と経済的働きの総量である。どちらにしても、微分積分に関係している。
我々は、学校では積分より、微分を先に習う。しかし、歴史的に見ると積分の成り立ちの方がずっと古い。積分は、面積を測る技術として発達してきたのである。
経済的現象においても量を測る手段として積分は有効である。
要するに、積分は、面積を計算する手段の一つである。
では、面積は何かという事である。我々は、面積というと図形によって形づけられた領域を思い浮かべるが、ここでいう面積とは、単純に、面積とは、物理的空間のみを指すわけではない。
積分は、多様な形の面積も細分化された長方形の面積を足し合わせた値と見なす事で成立した。
積分の働きや意味を考える場合、面積とは何かを考えるのは、有意義である。
我々は、面積というと形から思い浮かべるが、しかし、当初は、面積は、収穫量から導き出されていた。また、重量によって面積を求める事もあった。バビロニアでは、大麦、百八十粒の体積を一シュケルと言い、大麦百八十粒を蒔いた畑の広さを一シュケルとした。また、一シュケルは貨幣の単位でもあった。(「面積の発見」武藤徹著 岩波書店)
このように、面積や重量、貨幣単位は、複雑に関連しているのである。このことは、数学と経済との関係をも暗示している。
しかし、面積や体積を量る基準は、最初から正方形や立方形であったわけではない。例えば、任意に決められた一つの樽に入れられた石油の量(バレル)のような物が体積の基準だったりした。このような体積は、必然的に重量とも結びつけられていた。
又、ガロンは、水やワインに単位と関連してくる。
本来、単位の多くは、税金だの取引の為の基準だのとして扱われてきたのである。現実の世界では、最初から正方形や立方形をした物など殆どないのである。単位は、生活の実体験や必要性から生み出された尺度である。この点を理解しておかないと数学本来の意義が見失われてしまう。数学は、世の中の役に立たない学問でも、かけ離れた学問でもないのである。
今日、面積は、一般的には、二次平面に描かれた図形を元にして考えられている。
その場合の面積とは、ある一定の条件によって作られた空間の内部で線に囲まれた領域が占める空間の量を言うのである。
今日の面積の単位は、長さを掛け合わせた値である。
面積は、線に囲まれた領域と座標軸の位置の関係が重要な要素となる。座標軸の位置によって面積の値は、確定する。
面積は、次元によって点、線、面、体積、そして、多次元領域へと変換される。経済的領域は、多次元的な領域が多い。それ故に、経済的な面積とは、必然的に多次元的な領域になる。
故に、積分と微分の関係は、結局、次元操作の問題に集約される。
経済と面積は、一見、結びつかないように思える。しかし、経済現象は、面や体積としてとらえた方がわかりやすい長谷愛があるのである。
経済は、時間と貨幣の関数だといえる。すなわち、貨幣価値と時間軸によって描かれた面積を測る事が経済現象を理解する上で近道になる事が往々にしてある。
貨幣価値は、物の価値を表す側面と貨幣の価値そのものを表す側面とがある。物の価値は、貨幣価値の実質的価値を表し、貨幣の価値そのものは現金価値を表す。実質的価値は、単位となる単価と物の量からなる。現金価値とは、その時点時点に開ける貨幣の指し示す値を言う。
この貨幣価値の推移と時間軸によって囲まれた面積や体積が経済的価値の総量を表している。
故に、経済にとって積分は重要な意味を持っているのである。
断片を寄せ集めて複雑な形をした対象の面積や体積を求めようと言うのが積分であり。
また、点の積み上げ、線の積み上げ、面の積み上げる考え方が積分的思考である。点や線や面を集めたのが積分である。
面への分解、線への分解、点への分解する捉え方が、微分的思考である。線や面や体積を細かくしたのが微分である。
数直線の和が積分である。
経済現象を構成する要素は、数直線として表される。そして、時系列的に分解できる。量は積分によって、変化は微分の速度によって求められる。
市場経済で重要になるのは、市場の規模と市場の変化である。市場の規模は、物流の規模と人の欲求の規模と貨幣の流通量の規模との相関関係によって定まる。
微分は、変化を表し、積分は量を表す。
位置を微分すると速度になり、速度を微分すると加速度になる。加速度は力を表す。加速度を積分すると速度になり、速度を積分すると位置となる。
加速度は速度の微分係数、速度は位置の微分係数、つまり、加速度は位置の二階微分係数。又速度の積み重ねが位置(積分)を表し、加速度の積み重ねが速度(積分)になります。(「中学・高校物理のほんとうの使い道」京極一樹著 じっぴコンパックト新書)そして、加速度は力の係数である。
経済量を微分的な量として計算するか、積分的な量として計算するかは、市場の状態に基づかなければならない。
拡大している市場は、微分的に見る必要がある。成熟している市場は、積分的に考える必要がある。
我々は、二乗を平方(square number)という。三乗を立法という。
平方や立方は、図形的な意味だけではない。
積分は、位置エネルギー、総和、或いは、量を対象としている。それに対し、微分は、接点の働き、運動、変化、又は、方向を表している。
経済的変化は、連続量だと言うこと。そして、経済は時間の関数に置き換えられる。
例えば、同じ平面でも微分は変化を意味し、積分は量を意味する。
既知数、或いは、定数の数と未知数、或いは、変数の数が次元を決める。
積分や微分は、次元の変換をも意味する。
経済量は基本的に数量と単価の積である。単価とは、単位価格でもある。
積分で重要なのは積和である。即ち、積と和である。
即ち、積分の根底には群論が隠されている。
積分の大本は、積算である。
微分型産業、微分型経済から積分型産業、積分型経済へと切り替わる必要がある。微分型産業とは、産業の成長速度が市場の成長率に比例している産業を言う。積分型産業とは、それまでの生産活動の総量によって生産量が決まる産業をいう。
つまり、微分型というのは、成長、則ち、変化に依拠した経済であるのに対し、積分型産業とは、生産量に基づいた経済を意味する。
現在の経済は、成長や技術革新が恒久的に続くことを前提として成り立っている。しかし、成長や技術革新が恒久的に続くという確証はどこにもない。仮に、技術革新や成長が続くとしても切れ目なく成長や技術革新が続かなければ、経済は停滞に落ち込んでしまう。
肝腎なのは、国民が人間としての最低限の生活を維持し、更に、自己実現に必要な資源を生産し、分配できることが出来るような経済の仕組みを構築することなのである。
積分は面積を測る手段として確立された。これは、経済の規模を測るための手段として積分が有効であることを意味している。
人間は、自分の限界に気がついた時、無限の世界を知る事が出きる。それは自分が有限の世界にいるからである。限りある自分を知った時、無限の世界を受け容れざるを得ないのである。
故に、無限は、神の世界の領域の問題なのである。それを前提として無限は考察されるべき問題である。
怖れ、そして、敬い、信じる世界、それが無限の世界である。無限とは、神秘な対象なのである。



このホームページはリンク・フリーです
ページの著作権は全て制作者の小谷野敬一郎に属しますので、一切の無断転載を禁じます。
The Copyright of these webpages including all the tables, figures and pictures
belongs the author, Keiichirou Koyano.Don't reproduce any copyright withiout
permission of the author.Thanks.
Copyright(C) 2009.12.20 Keiichirou Koyano